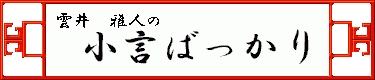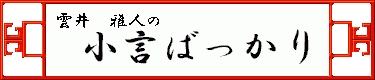|
2004/05/16(日)
離陸
|
「G線上のアリア」、「ヘンデルのラルゴ」、「アルビノーニのアダージョ」、「亡き王女のためのパヴァーヌ」、「スカルラッティのすみれ」、「浜辺の歌」、「グノーのアヴェ・マリア」、「ラフマニノフのヴォカリーズ」。ラジオやレコード、CDから流れてくる美しい旋律に魅せられて、自分もそれを演奏してみたいと願うのは、ちょっとでも楽器をいじったことのある人なら、当然持つ欲求でしょう。
僕もそうでした。若い時から、「グノーのアヴェ・マリア」が特に好きで、友だちの伴奏でよく吹いていました。ところが、なぜか自分で吹くとレコードのような感動がちっともない。「おかしいな、こんなはずではないのに。もっといい曲のはずなのに」とうすうす感じつつ吹いていた気がします。
今から考えると信じられないようなことなのですが、そのころ僕は、“自分の音が悪いということに気付いていなかった”ようなのです。まことにもって愚かでした。
極端に言えば、「自分はそこそこの音をしている。だから名旋律を吹けば名演奏になるだろう」と思っていたようなのです。この病気はそうとう根が深かったらしく、留学から帰って数回のリサイタルを経たのちも症状に気付くことなく、治癒するのに長い時間がかかりました。演奏会のアンコールに、貧相な音で「浜辺の歌」や「ヘンデルのラルゴ」をやって、恬として恥じることがなかったのでした。本当はこういう曲の方がコワイのに。
良い音の秘訣はブレス(呼吸)にある、ということに気付いたのはかなり後になってからでした。ブレスの重要性を頭で分かってはいても、それを実感するのは難しいことです。
僕の場合は、「自分の音には大して魅力がない」ということに気付き、嫌悪感すら持ちはじめていたことが伏線でした。そして、あるとき合唱指揮者の関屋晋氏が女声コーラスを指導されている場面をテレビで見たことで、大切な何かが分かったのです。関屋氏は、メンバーに「みぞおちを指先で軽く押さえて咳払いをしてごらん」というアドバイスを与えていました。それが、僕のブレスのシステムを入れ替えるきっかけになった瞬間でした。
大学などでレッスンをしていて、ある日生徒が良い音を出し始めるときがあります。そんなとき僕は、「この人は離陸しはじめた」と感じます。音がごく自然な感じで楽器から離れて、飛ぶ感じがするのです。逆に、響かない音は、離陸できず胴体を地面にこすっているような感じがします。
飛びはじめてからの音が、真にその人固有の音であり、その人にしか出せない本当の音です。音楽の楽しみは、そうなってからの方がより深いのです。生徒たちには、自分の音をぜひ追及していって欲しいものです。
|
|